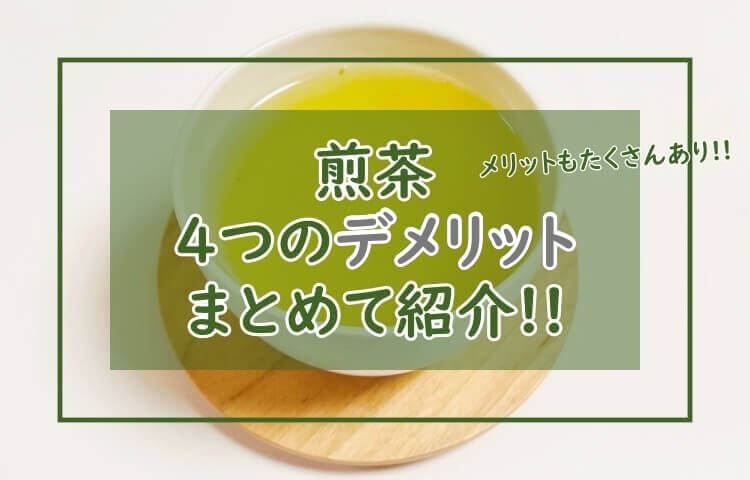- 煎茶にデメリットはあるの!?
デザート級に美味しい煎茶ですが、欠点を挙げるなら!と思う4つを紹介。
煎茶のデメリット4つ!
- カフェインを含むこと
- カテキンの摂りすぎ注意
- 淹れ方が難しい
- 風味が落ちやすい
特にカフェインは要注意。
カテキンや賞味期限など、気になる点もあるので、煎茶の知識として参考にしてみてください^^

この記事では、緑茶の仲間「煎茶」のデメリット詳細やメリット、デメリット対策をまとめてみました!
煎茶のデメリット詳細!

煎茶のデメリットは、茶葉に含まれる成分や特徴から来るものが多め。
(淹れ方も少し難しい!)
デメリット1:カフェインを含む
一番のデメリットが「カフェイン」を含むこと。
「緑茶=カフェインを含む」イメージが強いですが、煎茶はその代表格ではと。

実際どのくらいカフェインを含むの?
と調べてみると(日本食品標準成分表参考)、煎茶に含まれるカフェイン量は「1杯約20mg」とのこと。(茶葉10g・90℃・湯量430ml・抽出時間1分)

と疑問に思ったので、1日の上限を確認。
食品安全の基本とカフェインの安全性についてを参考にすると、健康な成人のカフェイン摂取量は「400mg/日」とのこと。

ただ、煎茶は淹れ方や種類によってもカフェイン含有量が変わります。
なので参考値程度の認識で良いかと。

ちなみに同資料曰く「寝る前→100mg以内」「妊婦さん→200mg以内」と記載あり。
寝る前に緑茶って飲んでいいの?
妊婦はどこまで飲んでいいの?
とった方は、参考程度になると思います!
デメリット①まとめ
・煎茶はしっかりカフェインを含む
・1杯で約20mg含む(茶葉10g・90℃・抽出1分)
・健康な成人は1日約20杯ほど(上限400mg)
・妊婦さんは1日約10杯ほど(上限200mg)
・寝る前は約5杯まで(上限100mg)
ただし、淹れ方で含有量が変わる事、カフェインを含む食べ物(チョコレートなど)にも注意が必要!
デメリット2:カテキンのとりすぎ注意!
煎茶に含まれる「カテキン」にも、デメリットの可能性があるので一応注意を。(ただし可能性レベル)
2007年にカナダ保健省は、茶抽出物を含むサプリメントを摂取した方のうち、肝機能障害が生じた事例を報告しました
読むと怖いですが(笑)茶カテキンとの因果関係は明らかになっていないとのこと。
確信はなさそうですが、気になる方は注意した方がよいかと。

と気になったので、Kaoさんの資料を調べてみると「1000mg~1500mg」内では問題なさそう。
日本食品標準成分表内では、煎茶に含まれるカテキン(=タンニン)量は「1杯約70mg」とのこと。(茶葉10g・90℃・湯量430ml・抽出時間1分)

カフェインほど気にする必要はないかと。
過剰摂取にならない程度で問題なさそう!
デメリット②まとめ
・カテキンも過剰摂取に注意
・ただ多めに見積もっても10杯/日は行けそう
・上限はカフェインの方がキツイ。ので過剰摂取にならない意識でOK!
デメリット3:淹れ方が難しい
淹れ方が少し難しいのも多少デメリット。
ほうじ茶・玄米茶→100℃のお湯でサッと注ぐだけ
煎茶→70℃~80℃に湯冷まし後、抽出時間に注意
くらいの違いあり。


特に沸騰したてのお湯だと、苦みや渋みが出ます。
本来の味を楽しむためにも、手間を惜しまず淹れることが大切!
デメリット③まとめ
・煎茶は湯温・抽出時間に注意する必要あり
・逆に手間を楽しむくらいの感じで!
デメリット4:風味が落ちやすい
ほうじ茶などと比較すると、風味が早く落ちやすいのも少しデメリット。
季節や茶葉の種類にも寄りますが、大好きな茶葉ほど、落ちた風味にすぐ気づきます(笑)

ほうじ茶は短くても3ヵ月程度、普通は半年は持つ感じ。
少しでも風味を保つために、保存環境にこだわりましょう!

デメリット④まとめ
・賞味期限は約1ヶ月(季節・保存環境にもよる)
・ほうじ茶等(3ヵ月~半年)より短め
・保存環境にこだわって、風味を保とう!
もちろん煎茶にはメリットもある!
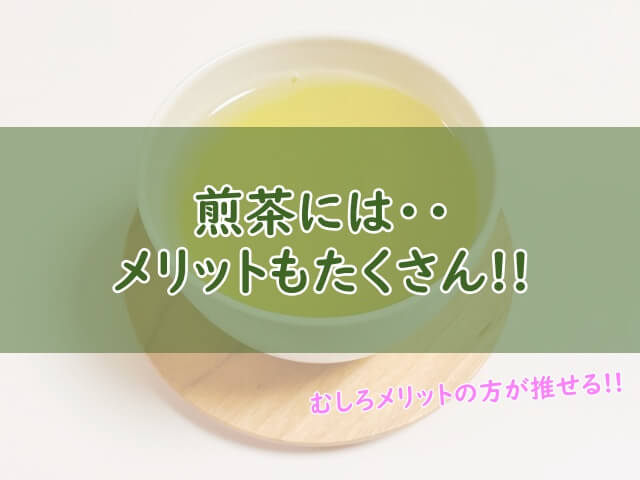
デメリットを詳しく紹介しましたが、煎茶にはメリットも当然あり!
(超美味しい!は例外)
メリット1:カフェインでお目覚め!
デメリットで紹介したカフェインですが、実はメリットもあり。
煎茶のカフェインにはメリットもあり!
- 朝をしゃっきりさせる!
- 集中力をアップ!
などなど、頭のキレに期待あり!


朝、煎茶を飲んでしゃきっと動く!みたいな期待もできるので、朝茶は超おすすめ!
摂りすぎるとデメリットになるカフェインですが、紹介した上限以内で飲めばメリットたくさん!
メリット2:体に嬉しいカテキン!
カテキンもデメリットで紹介しましたが、そもそもメリットだらけのスーパー成分。
・抗酸化作用
・抗ウイルス作用
・抗ガン作用
・コレステロールを下げる作用
・血糖の上昇を抑える作用
・殺菌作用・抗菌作用
・虫歯・口臭予防
・肥満予防
引用健康長寿ネット

カテキンを含む食品はいくつかありますが、緑茶はかなり取りやすい食品。
「緑茶を毎日飲むと、体に嬉しいことがたくさん!」
と言われますが、カテキンパワーのおかげかな?と。

メリット3:いろんな味が出せる!
淹れ方(お湯の温度・抽出時間・茶葉の量など)の工夫次第で、いろんな味が楽しめるのも煎茶のメリット!
(デメリットで「淹れ方が難しい」とか言ったのに笑)


といった感じで、同じ茶葉でも違う味が出せます。
ほうじ茶などは、煎茶ほど変化が楽しめないので、素敵なメリット!
煎茶のデメリット対策案!
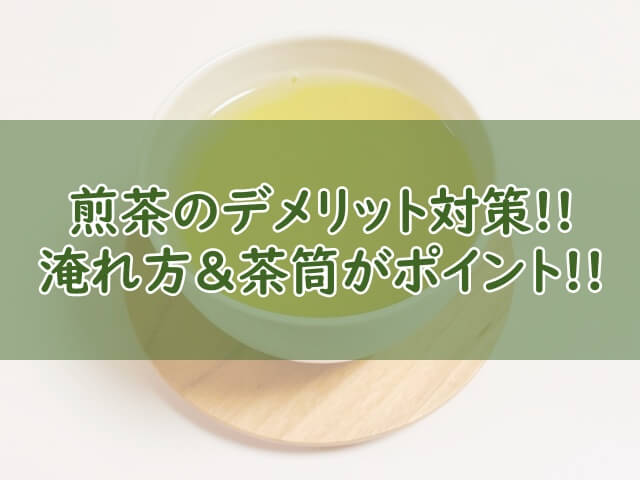
煎茶のデメリットで紹介した・・
ほうじ茶デメリット対策!
- カフェイン・カテキンの量
- 淹れ方が難しい
- 風味が落ちる
の3つについて対策案を紹介!
【デメリット対策1】淹れ方を変えてカフェイン・カテキン量を調整!
カフェイン・カテキンを少なくするなら、淹れ方を工夫しましょう!
| カフェイン・カテキン量を減らす淹れ方! | |
| お湯の温度を下げる | カフェイン・カテキンが高温に溶けにくいため |
| 蒸らす時間を短くする | 成分が溶ける量を減らすため |
| 茶葉の量を減らす | 成分が溶ける量を減らすため |
カフェイン・カテキンとも「高温に溶けやすい」ため、お湯の温度を下げると抽出量が減ります。

また、茶葉をお湯に浸す(蒸らす)時間が短いだけ、溶け出す成分も少な目に。茶葉の量を減らすのも同じ!
【デメリット対策2】美味しい緑茶の淹れ方をざっくり知る!
美味しいお茶が淹れられない!
という方には、今すぐできる淹れ方ポイントをご紹介。
| 美味しい淹れ方ざっくり版 | |
| 甘み・旨みが欲しい! | お湯の温度を下げる・蒸らす時間を短く |
| 渋み・苦みが欲しい! | お湯の温度を上げる・蒸らす時間を長く |
まろやか~な味が好きな人は「お湯の温度を下げるか、蒸らす時間を短く」しましょう。
苦味・渋みが好きな人は「お湯の温度を上げるか、蒸らす時間を長く」しましょう。
【デメリット対策3】茶筒を使って風味を保つ!
茶葉の風味を保つポイントは、保存環境の調整。
- 高温・多湿を避ける
- 香りの強い場所を避ける
- 光を当てない
が保存のポイント。
高温・多湿を避けるには、廊下などの場所がおすすめ。
香りや光の遮断には、茶葉専用保存容器「茶筒」を使うと良いかと!
>>おしゃれで機能高めの茶筒を紹介中!【自称茶筒コレクター(笑)紹介】
煎茶のメリット・デメリット紹介でした!
ほうじ茶のデメリット・メリットも紹介!!
-

-
ほうじ茶の【デメリット】を3つ紹介!もちろんメリットもある!
続きを見る
メリットたくさん!!番茶が良い!!
-

-
番茶のメリットは?優しいお茶を飲みたい人はおすすめです!
続きを見る
玄米茶のデメリット・メリットも紹介!!
-

-
玄米茶ってどんなお茶?香ばしさが魅力的!デメリットはあるの?
続きを見る